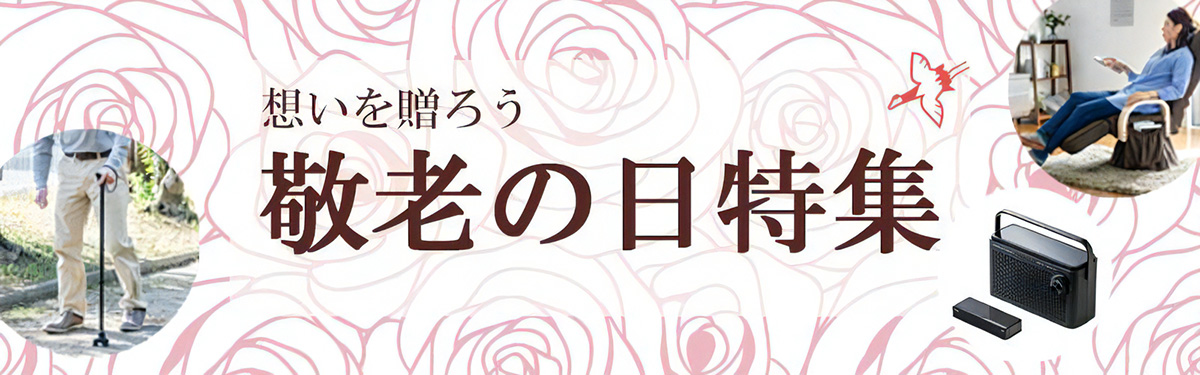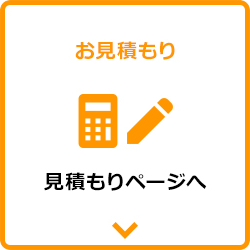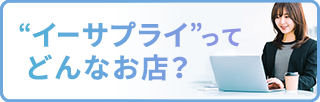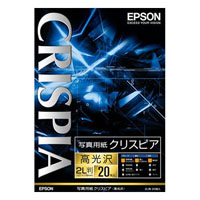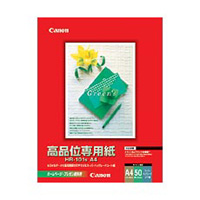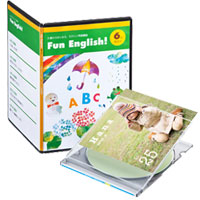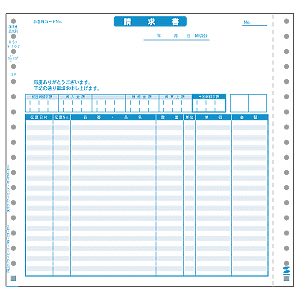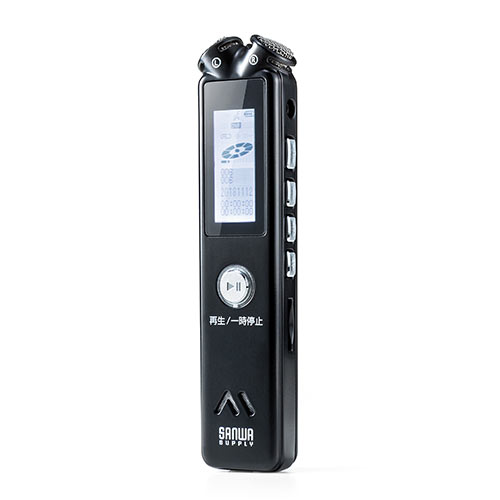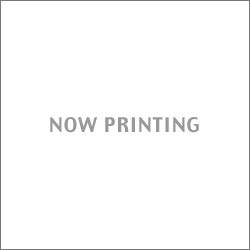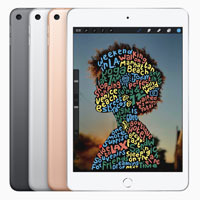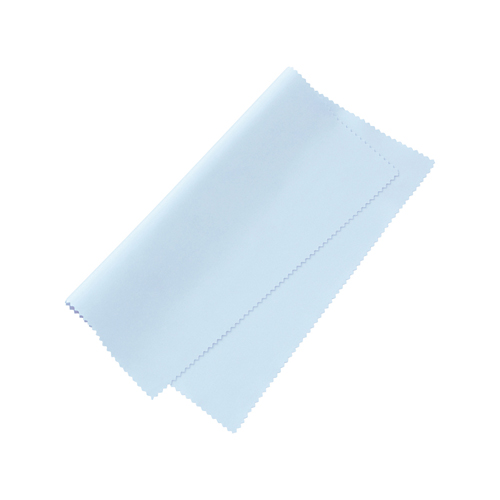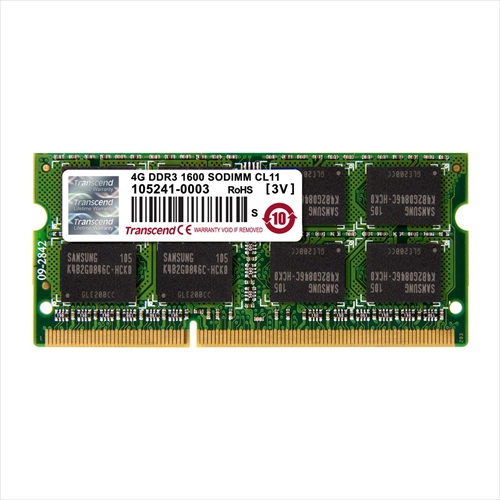2025年と今後の敬老の日はいつ?
まずは、皆さんが一番気になっている「敬老の日がいつなのか」という情報からお伝えします。
土日と合わせて3連休になるため、家族で集まったり、少し遠出をしたりする計画も立てやすいですね。
敬老の日は毎年9月の第3月曜日
敬老の日が毎年違う日付になるのは、「ハッピーマンデー制度」によって「9月の第3月曜日」と定められているためです。
もともと敬老の日は9月15日に固定されていましたが、2003年から現在の形になりました。これにより、多くの人が週末と合わせて連休を取得しやすくなっています。
敬老の日とは?意味・由来と「老人の日」との違い
敬老の日がいつかわかったところで、次はその意味や由来について見ていきましょう。背景を知ることで、より一層心を込めてお祝いができるようになります。
敬老の日の意味と目的
敬老の日は、「国民の祝日に関する法律」において、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日と定められています。
単に長寿をお祝いするだけでなく、これまで社会を支えてきてくれたお年寄りへの感謝と尊敬の気持ちを表す、とても大切な日なのです。
「老人の日」との明確な違い
「敬老の日」とよく似た言葉に「老人の日」がありますが、この2つは明確に異なります。
老人週間は9月15日(老人の日)から21日までの1週間を指します。国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるために設けられています。
もともと9月15日だった「敬老の日」がハッピーマンデー制度で移動したため、その日を記念する形で「老人の日」が新たに作られました。祝日としてお祝いするのは「敬老の日」と覚えておきましょう。
敬老の日は何歳から祝う?年齢の目安
「敬老の日って、何歳からお祝いするものなの?」という疑問は、多くの人が抱く悩みの一つです。ここでは、お祝いを始める年齢の目安について解説します。
お祝いする年齢に明確な決まりはない
まず知っておきたいのは、「何歳から敬老の日を祝う」という法律やルール上の決まりは一切ないということです。そのため、お祝いする側・される側の気持ちや関係性によって、自由に決めて問題ありません。
しかし、「年寄り扱いされたくない」と感じる方もいるため、相手の気持ちを配慮することが大切です。
60代・70代からが一般的な目安
一般的には、還暦(60歳)や古希(70歳)といった長寿のお祝いの節目を迎える60代・70代から敬老の日のお祝いを始めるケースが多いようです。
特に70歳を過ぎると、多くの方がお祝いを自然に受け入れやすくなると言われています。
孫の誕生をきっかけにする考え方
もう一つの素敵な考え方が、「孫が生まれたタイミング」をきっかけにすることです。子どもから「おじいちゃん、おばあちゃん、いつもありがとう」という形でプレゼントを渡せば、年齢を意識させることなく、自然な形でお祝いができます。
「何歳から」と悩んだら、おじいちゃん・おばあちゃんになった年をスタートの年にするのは、とても良いきっかけになるでしょう。
敬老の日の祝い方・過ごし方アイデア
敬老の日は、プレゼントを贈るだけでなく、さまざまな形でお祝いできます。ここでは、定番から心温まるアイデアまで、具体的な祝い方をご紹介します。
定番からユニークなプレゼントのアイデア
何を贈れば喜んでもらえるか、プレゼント選びは楽しい悩みの一つです。
家具
毎日使う椅子は、実用的で長く愛用できるプレゼント。リクライニング機能付きやクッション性の高いタイプなど、体にやさしく快適に過ごせる"くつろぎの時間"を贈りましょう。
テレビスピーカー
音が聞き取りやすくなるテレビスピーカーは、映画やドラマをもっと楽しめる優秀アイテム。耳元スピーカーや声がクリアに聞こえる機能付きモデルなど、年配の方にぴったりです。
花束・フラワーギフト
感謝の気持ちを華やかに伝えられる花束は、定番ながらも喜ばれるプレゼントです。リンドウや秋桜(コスモス)など、秋らしい季節の花を選ぶのがおすすめです。
お菓子・グルメギフト
少し高級なお菓子や、普段は食べないような特別感のあるグルメギフトも人気です。相手の好みに合わせて、和菓子や洋菓子、お肉やお魚などを選びましょう。
健康グッズ・マッサージ機器
「いつまでも元気でいてね」という気持ちを込めて、マッサージクッションや血圧計などの健康グッズを贈るのも良いでしょう。手軽に使えるものが喜ばれます。
趣味に関する実用的なアイテム
ウォーキングが趣味なら新しいシューズ、読書が好きならブックカバーや拡大鏡など、相手の趣味に合わせた実用的なアイテムは「自分のことを考えて選んでくれた」という気持ちが伝わります。
プレゼント以外の祝い方
物だけでなく、一緒に過ごす時間や言葉で感謝を伝える方法も素晴らしいお祝いです。
一緒に食事会や旅行をする
家族みんなで集まって食事をしたり、近場の温泉に一泊旅行したりするのも素敵な思い出になります。大切なのは、おじいちゃん・おばあちゃんの体調に無理のない範囲で計画することです。
感謝の手紙やメッセージカードを渡す
普段は照れくさくて言えない感謝の言葉も、手紙なら素直に伝えられます。特にお孫さんが書いた似顔絵やメッセージは、何よりの宝物になるでしょう。
電話やビデオ通話で感謝を伝える
遠方に住んでいて直接会えない場合は、電話やビデオ通話で元気な顔を見せながら話すだけでも、とても喜ばれます。「いつもありがとう」の一言を、ぜひ声で届けてあげてください。
敬老の日のプレゼント予算・金額相場
プレゼントを贈る際に気になるのが予算です。関係性によって相場は少し異なりますが、一般的な目安をご紹介します。
祖父母への相場は3,000円から5,000円
お孫さんからおじいちゃん・おばあちゃんへ贈る場合の予算は、3,000円~5,000円程度が一般的です。高価すぎるとかえって気を遣わせてしまうこともあるため、気持ちが伝わる範囲で選びましょう。
両親への相場は5,000円から10,000円
ご自身の親へ贈る場合は、5,000円~10,000円程度が相場とされています。兄弟姉妹でお金を出し合って、少し豪華なプレゼントや食事会を企画するのも良い方法です。
最も大切なのは金額ではなく、感謝の気持ちです。予算はあくまで目安として参考にしてください。
敬老の日に関するQ&A
最後に、敬老の日に関してよくある質問にお答えします。
メッセージで大切なのは、具体的なエピソードを交えながら感謝を伝えることです。
直接会えない場合は、以下のような方法でお祝いするのがおすすめです。
- プレゼントや手紙を郵送する
- 電話やビデオ通話で話す
- カタログギフトを贈って、好きなものを選んでもらう
- デリバリーサービスを利用して、当日にご馳走を届ける
大切なのは、離れていても気にかけているという気持ちを伝えることです。
この記事を参考に、ぜひ今年はあなたらしい方法で、大切な方へ感謝を伝えてみてください。